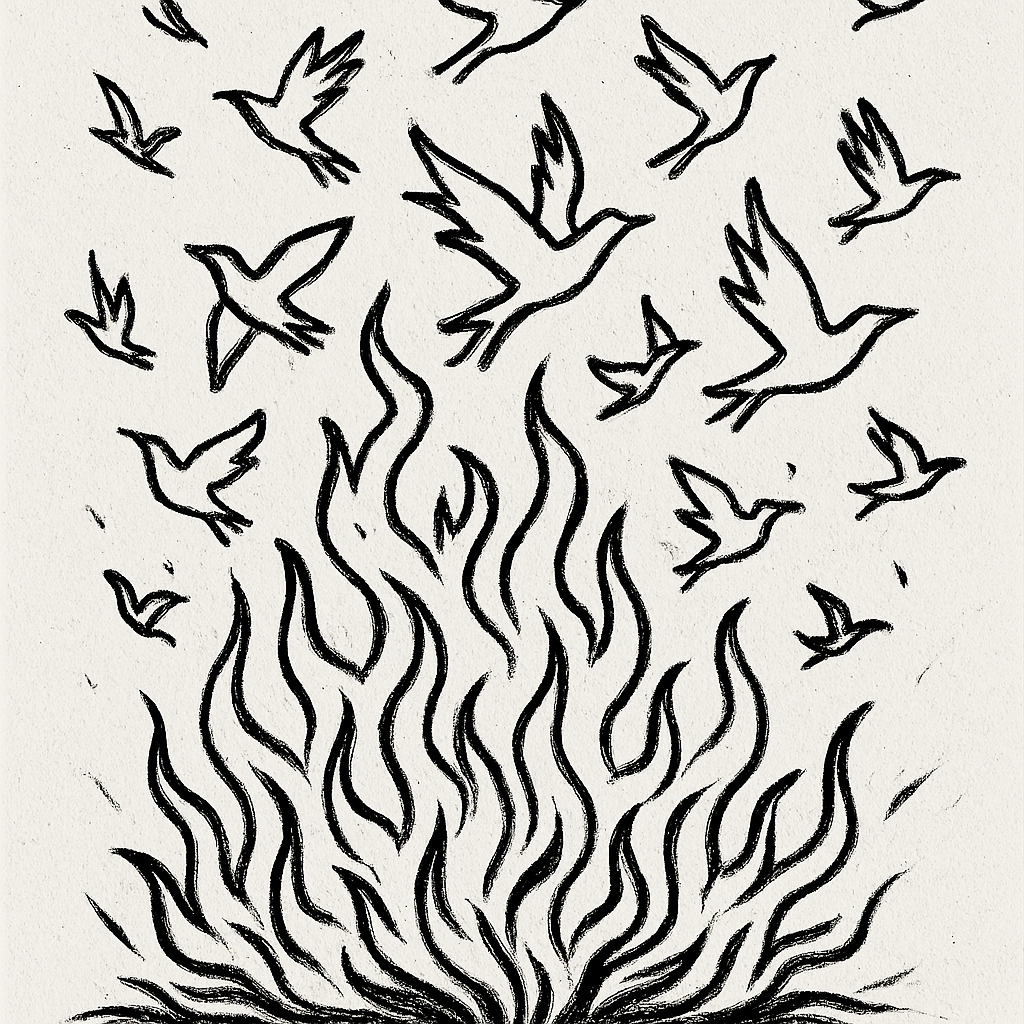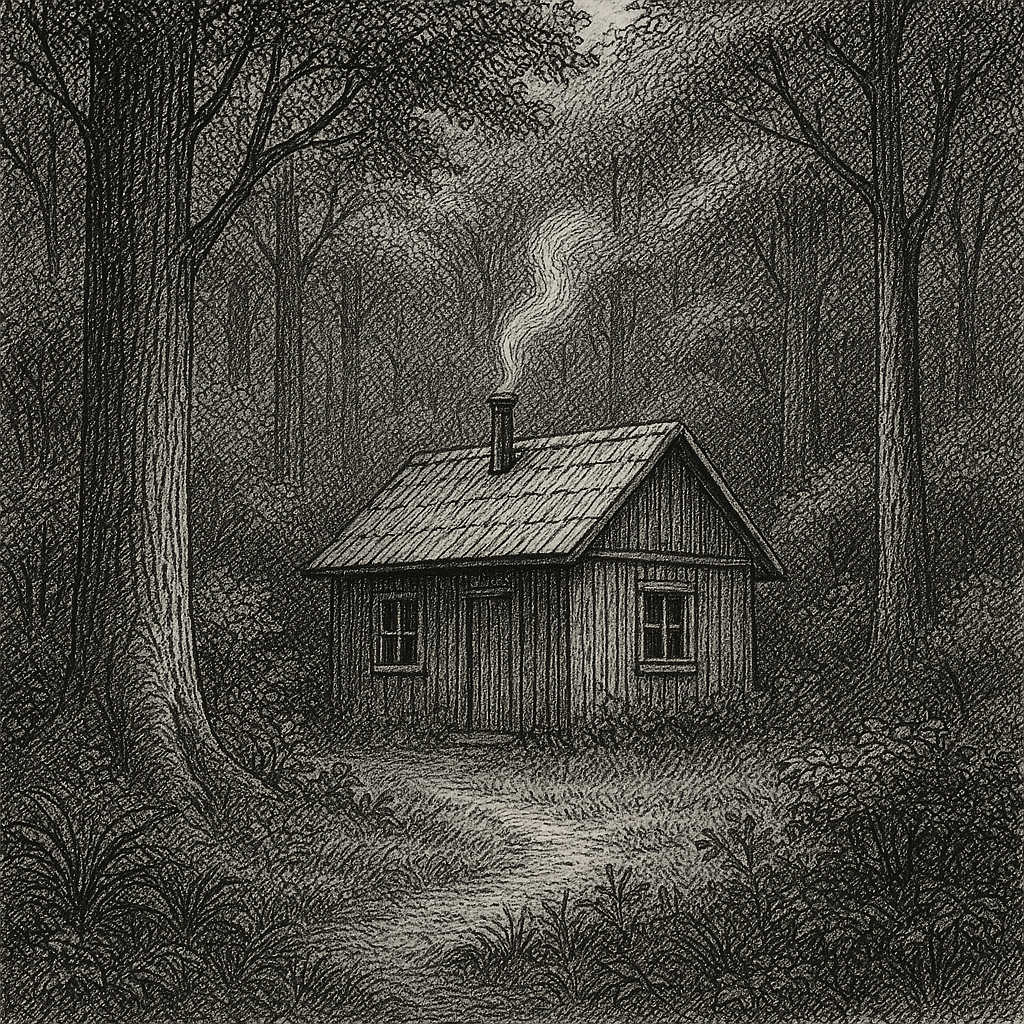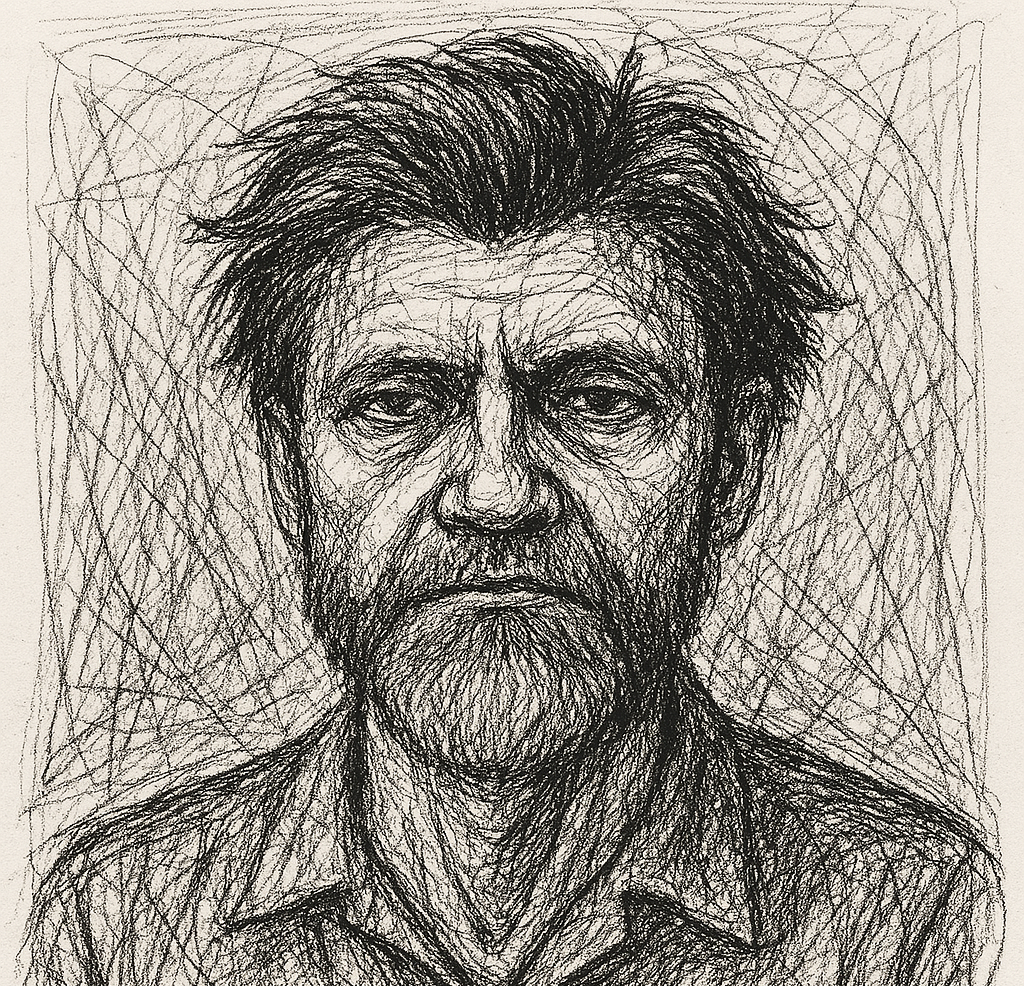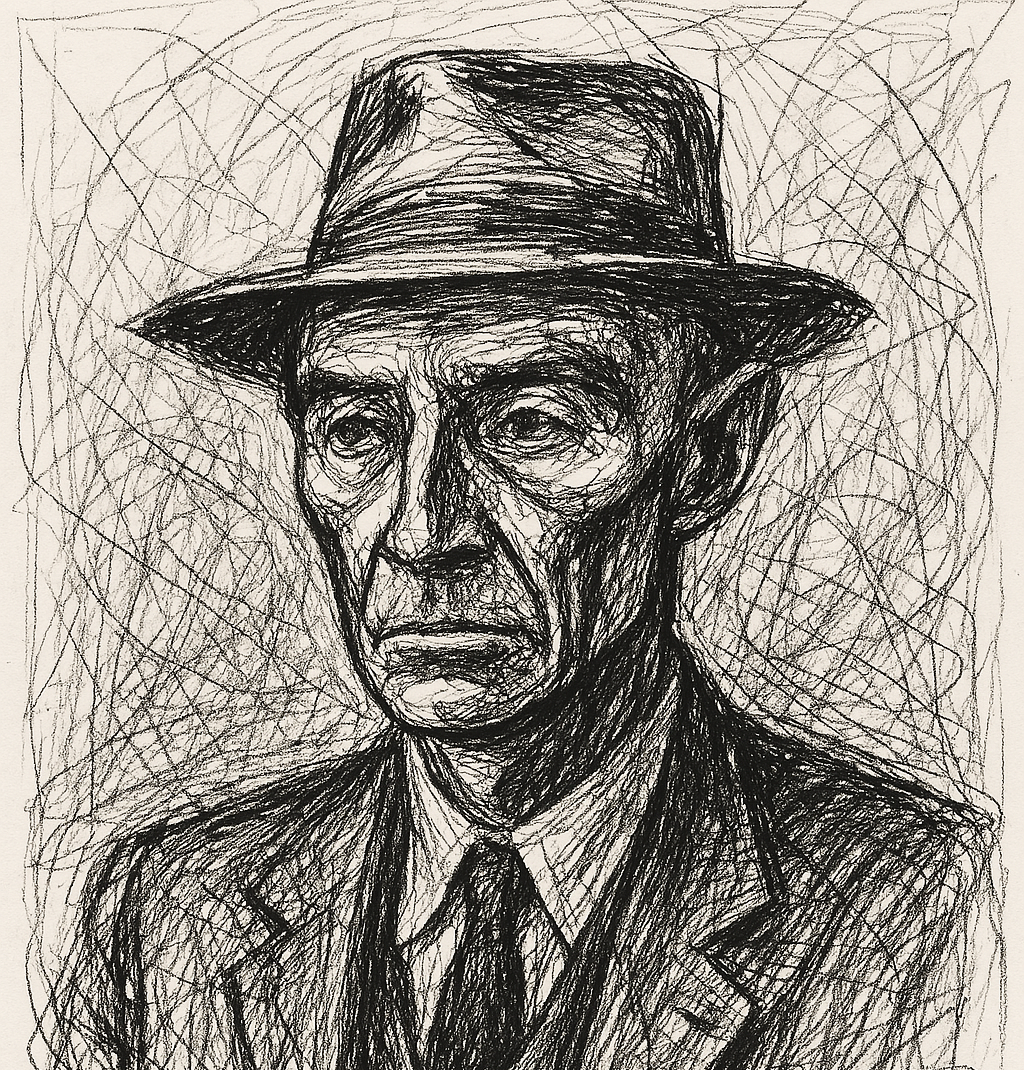Authored by 円原一夫
ようやく『君たちはどう生きるか』を観ることができた。およそ、粗筋やキャスト、舞台について何も知らずに映画を観ることがなかったため、まずその点で新鮮な体験だった。とはいえ、とにかく私はこれを宮崎駿の作品であるということだけは、確かに、知っていた。
宮崎駿の作品に共通するのは、その、日本中の家族を動員するほどの、ある種の単純さである。シンプル・イズ・ベスト。俺は褒めてんだぜ(立川談志)。『風立ちぬ』のような作品を除けば、宮崎駿の映画作品は概ね、「オールドな啓蒙主義」の作品であり、ビルドゥングスロマンであり、「行きて帰りし物語」である。少女が異世界で労働を通して成長し、日常へ戻って僅かに世界を改善する(『千と千尋の神隠し』を想起せよ)。
そして、この『君たちはどう生きるか』もまた、「オールドな啓蒙主義」の装いを保っていた。だから、宮崎駿が好きなものは、『風立ちぬ』に拒否反応を示したものも、面白く観ることができるだろう。
しかし私は『君たちはどう生きるか』を「オールドな啓蒙主義」を面白おかしく説明するための題材にするような真似はしない。批評は認識の革命である。批評は、あなたが自分が本当には『君たちはどう生きるか』を観ていなかったと悟らせ、もう一度、劇場に足を運ばせる。そう、私はこれが「オールドな啓蒙主義」の装いを保ちつつ、「オールドな啓蒙主義」を超えた作品であると、あなたに言いたいのだ。つまり傑作である、と――。
そのために私が考えてみたいのは、何故、あの塔の中の世界では妊婦である夏子に近づくことが禁忌とされていたのかということである。幾つかの台詞で、しつこく、夏子の腹の中に子どもがいるため、接触が禁止されていると説明され、そしてその侵犯が物語をさらに進める。インコですらもが、子どもが腹の中にいるため夏子を食べようとはしない。
この「禁忌」の謎を、私がこの作品を分析するために選んだのは、必ずしも恣意的なものではない。偉大な法学者ハンス・ケルゼンは、法規範の最終的な根拠、あらゆる法規範を妥当なものとする最上位の法規範である根本規範という概念を提唱したが、私はこの「禁忌」の分析を通して、あの世界の根本規範を素描しようと企図しているのである。
さて、結論から書けば、これは赤児が「無垢」であるためなのである。あの異世界は無垢な者が構築し、悪意の汚れのある者たちが運用・保守しなくてはならない世界としてある。ペリカンはそれを「地獄」と言ったのだ。無垢な者などこの世界に存在しないのだから。そう、始めから全てが間違えている。だから、「地獄」。
あの世界の根本規範を考えるための、今ひとつの材料は、眞人が何故、あの世界の次代の創造者に選ばれ、そして、それを彼が何故、断ったかということである。そして、前者の疑問への答えが「無垢であるから」であり、「実は無垢ではなかったから」なのだ。無垢、無垢、無垢。これが今回のこの映画の根本規範だ。
あなたは、このような疑問を持ってよい。例えば、何故、次代の創造者は「ヒミ」や「キリコさん」、「夏子」ではなく、眞人なのだろうか?
ここでもまた考えなければならないのは、「無垢」である。「ヒミ」は実は主人公の母であり、「キリコさん」は眞人の母の屋敷に勤めていた女中なのである。「ヒミ」が何故、あの塔の中の異世界に入ったのかは明示的には描かれていないが、重要なのは、「キリコさん」を伴っていることである。彼女は女中を伴って、塔の中に入ったのだ。間違いなく地方の名士の娘である彼女が、塔の中の異世界でも召使い(と主人の関係)を必要とした人間であると想像するのは、私のプロレタリア的嫉妬のためだろうか。そして、塔の中で、「キリコさん」は自らは殺生しない「無垢」な者たちに肉を提供するため漁に従事し、「ヒミ」は(恐らくは)塔の中の循環の維持のために連れてこられ、致し方なく「わらわら」を食べているペリカンを火炎で追い払い、火傷で殺すような労働に従事している。そして夏子は家庭を放棄して、塔の中に入り、やがて訪れた義理の息子を危険に曝す。
安心してください。私はまだ主人公と彼女たちの決定的な差異について解き明かしてませんよ。
彼女たちと眞人の差異は何だろうか? 私たちが想起すべきは、眞人は「予め」次代の創造者だったわけではないということである。そうだとすれば、映画が1時間で終わってしまう。彼は「大叔父」に案内を依頼された「アオサギ」に連れられて、あの世界を冒険しなければならない。冒険して、最も危険な場所である「夏子」のいる部屋に入る。彼は彼女を「夏子母さん」と呼ぶ。主人公の父親の再婚相手である夏子を、複合名詞である「『夏子』『母さん』」と呼んで、母の喪失を彼なりに乗り越えようとする。
これこそ、主人公と彼女たちの差異が明白になった瞬間であった。冒険は継承者の選定に必要な過程であった。主人公だけが自分のためにではなく、誰かのために塔の中の世界に入ったことが明らかになった。彼は「悪意のない」積み木を渡され、塔の世界の継承者になることを求められる。
しかし彼はそれを拒否する。「この傷は自分でつけました」。彼は疎開先の学校で喧嘩をした帰り道、自分で自分の頭を石で殴り、大きな傷を作る。その傷のことを、「大叔父」に伝えて、オファーを断る。
この傷が「大叔父」からのオファーを断る理由になるのは、次のような状況のためである。実に宮崎駿は細部にまで「無垢」というテーマを徹底した。この映画は戦時中が舞台であり、そして眞人の父親は軍需工場のオーナーなのである。木村拓哉演じる彼は、眞人を心配して(勤労奉仕という意味のないことをしている)学校には行かなくていいと言ったり、日本軍が苦戦していることを正確に認識しているような、実に物分りのいい、頼りになる、良き父であるのだが、しかしまた、たしかに軍需工場のオーナーであり、日本軍の苦戦による需要の増大を喜びもし、そして「父」らしく、妻の死による家庭の混乱を直ちに妻の妹との結婚で平定するような人間でもある。眞人が喧嘩をしたのは明らかに、軍需工場のオーナーの家族とは生活水準で差があり、自分たちの農地から労働力を奪い去る戦争の最中にあっても、軍需工場で労働するか、農地を耕すしかない人々の子弟であった。
つまり「この傷は自分でつけました」という台詞は、また、「私は自分を罰しました」と言っていることに等しい。「無垢な者などいない」と言っていることに等しい。自分の利益のために何かをしないなど、無垢であることの証明にはなりはしない。ましてや、少年であることなど。眞人は既にペリカンを埋葬しているのであり、この台詞で、オファーの拒否で、無垢な者が世界を構築すれば世界は良くなるという大叔父の発想があまりにも無邪気であることを指摘したのである。大叔父も、静かに、眞人のオファーの拒否を肯定するより他にはなく、ひいては無垢な者が世界を構築するという自分のプロジェクトの崩壊を理解するより他にはない。だから彼はあの世界と運命をともにした。
さて、私は、この映画の最大のテーマが「無垢な者」であることを明らかにした。だから今では、あの塔の世界の禁忌が赤児との接触であるのは、赤児が無垢な者であるからだと、今、ここに書くことができ、そしてまた、そこから循環的に、あの世界にいる者は「ヒミ」ですらが赤児との接触を禁じられているからには、無垢な者ではないと言うことができるだろう。
そして赤児による統治も現実的ではない。私は行政学的、政治学的な統治行為の研究を引くつもりはない。この映画がそう言っているのだ。禁忌は破られたではないか。それも、「悪意のない積み木」の継承者に選ばれた者によって。そして赤児を崩壊する世界から外の世界に連れて出すのは、もちろん、「悪意のない積み木」の継承者には選ばれなかった女たちであった。
そう、世界は無垢な者たちが作るものではない。「ヒミ」は火の中に身を投じ、眞人と夏子は火で焼かれた後の東京へ帰る。世界は無垢な者たちのものではない。「この傷は自分でつけました」と言える者のものである。
啓蒙主義のプロジェクトは「蒙」を「啓」かれた者たちが良き世界のためには必要であると宣言したが、出現したのは「蒙」を「啓」かれた(と自称する)者たちによる地獄であった。現実に、ペリカンではなく人間が世界の維持のために必要だとして焼かれたのであり、焼かれている。
善き世界の構想ではなく、悪しき世界の継承。
言い換えれば、火の中に身を投じること、あるいは焼け跡に帰ること。
だがそれは映画の中で描かれたように、無垢であると観念されているような世界の大規模な崩壊なしには、現れないような人々によってだけ、可能なことだろう。