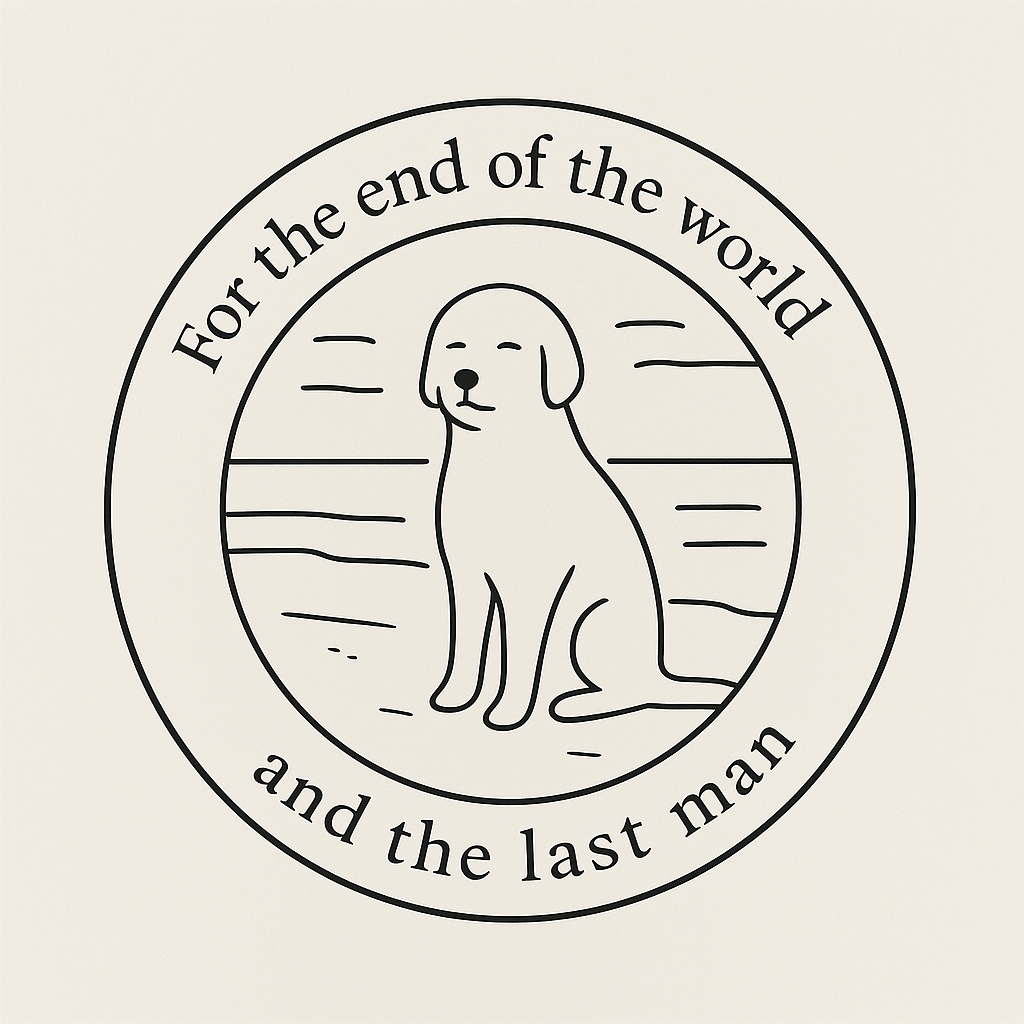1. 序論:近代公教育と国民形成の装置
近代日本の公教育は、明治維新という国家の一大転換期において、その根源的な性格を形成した。欧米列強による植民地化の危機を回避し、独立を保つための急速な近代化という国家プロジェクトにおいて、公教育は単なる知識伝達の場に留まらなかった。それは、徴兵制や税制などと並び、国家が「国民」という「想像の共同体」(ベネディクト・アンダーソン)を創出し、維持するための極めて重要な装置として機能したのである。
国家がその領域内で暴力を独占し、外敵に対する組織化された暴力のみを許容する「戦争機械」であるとするならば、それが基準を設定して実施する教育もまた、戦争を遂行するために国民という想像の共同体を再生産することに資するように作られていることは当然であり、自然であり、お望みならば、必要であったとすら言うことができるだろう。根源的な性格の形成とは、このことである。
さて、本稿では、近代公教育が国民形成に果たした役割を確認し、次に現代社会における「国民」共同体の変容を考察する。そして、その変容が公教育に突きつける構造的な対立と、そこから導かれる二つの根本的な選択肢について論じる。
2. 近代公教育の起源:国民を創る教育
明治維新後の日本において、公教育は強力な国家建設の手段として導入された。その目的は、封建的な身分制度を解体し、均質な国民意識を持つ近代的な国民を育成することにあった。
具体的には、標準語教育はその最たる例である。各地に多様な方言が存在する中で、共通の「標準語」を全国民に普及させることは、国民間のコミュニケーションを円滑にし、地域間の差異を超えた一体感を醸成するために不可欠であった。「国語」という科目の創設は、単に日本語の規範を教えるだけでなく、共通の文学や歴史を通じて、国民としての共通の記憶と価値観を内面化させる役割を担った。
また、共通のカリキュラムに基づいた学校経験は、すべての国民が同じ歴史や地理、道徳を学び、同じ規範意識を共有する場を提供した。これは、個々人がバラバラの存在ではなく、「日本人」という共通のアイデンティティを持つ共同体の一員であるという意識を育んだ。このプロセスは、国家のために命を捧げる国民兵を育成する徴兵の経験とパラレルであり、公教育が国家の「戦争機械」としての機能を支えるための基盤作りであったことを示唆している。つまり、公教育は、国家が国民を動員し、統制するための精神的・文化的インフラとして機能したのである。
3. 現代社会における「国民」共同体の変容と公教育の機能不全
しかし、現代において、この「国民という想像の共同体」は危機に瀕している。その背景には、第二次世界大戦以降の「長い平和」と、メディア環境の変化、そして経済思想の変遷が複雑に絡み合っている。
国際社会における第二次世界大戦以来の長い平和の期間は、戦争を遂行する巨大組織である国家というもののプレゼンスを著しく後退させた。共通の敵との対峙が稀になる中で、国家が国民に一体感を求める最大の求心力は薄れたのである。ソ連の消滅は、冷戦という対立構造の終焉を意味し、西側諸国は「勝利」したものの、同時に共通の脅威という求心力を失った。
この時期と並行して世界を席巻したのが新自由主義である。ケインズ経済学が国家による市場介入を重視したのに対し、新自由主義は「小さな政府」を志向し、市場の自由な働きを最大限に尊重した。これは、理念的には国家が自らの役割を縮小し、「自殺」するかのような印象を与えた。もちろん、レーガノミクスやサッチャリズムが軍事予算を通して国家を強大化させた側面は指摘できるが、少なくとも社会全体を包摂する福祉国家としての機能は弱められ、国民が国家に依存する意識は希薄化した。
国家の弱体化を単に福祉国家の弱体化に求めるのは根拠として弱い可能性がある。なぜなら、たとえ年金がなくても、いつでも志願できる巨大な軍隊があれば、それは究極の福祉であるという議論も可能だからである。より本質的な根拠として挙げられるのは、先進各国における直接税の比率の減少であろう。税こそは戦争機械の血液であり、同じ血液によって福祉国家も支えられてきた。味方の兵士のために自己犠牲精神を発揮するのと同様に「同じ国民が貧困や病で苦しむことは許せない」という連帯の感情によって私的所有権の一部制限が許容されてきたのであった。しかし、直接税の比率が減少していることは、このような意識の基盤が崩れ始めているということ、言い換えれば、人々が国民という想像の共同体のために自分の財産を減らしたくないという、共同体意識の弱体化を示す強力な証拠となる。
さらに身近な例として、ふるさと納税という我が国の奇妙な取り組みに言及してもよいだろう。この返礼品付きの住民税納付システムは、自分の居住する地域へ国民や市民という名目で徴税されることへの抵抗感、すなわち「想像の共同体」の弱体化に根ざしていることは明らかである。多くの納税者が、地域の住民サービスよりも返礼品の魅力を優先するこの傾向は、共同体への貢献意識よりも個人の実利を追求する「消費者」的な視点が優位に立っていることを示唆している。
4. 公教育の未来への選択肢:根本的変革か、環境の変革か
以上の考察から、近代公教育の起源から導かれる「国民形成」というその本質的な性格と、現代社会の環境は鋭く対立していることが明らかである。この乖離を解消するために公教育が取りうる道は、次の二択しかない。
第一の選択肢は、起源から導かれる性格の通りに公教育を再建することである。これは、国家が「戦争機械」としての性格を強く取り戻し、国民に共通の脅威を明確に提示することで、公教育が再びそのための強力な装置として機能する方向性である。だから、これは、これまで享受してきた平和を根本から覆す、極めてドラスティックでラディカルな環境の変化が必要となる。
第二の選択肢は、公教育の性格を根本的に変更することである。これは、かつて寺子屋が粉砕され国民学校になったように、現代の公教育に対してラディカルでドラスティックな変更を迫るものである。当然ながら、その領域で生計を立てる人々(教師、教育行政官など)からは猛烈な抵抗を受けるであろう。寺子屋を破壊した者たちの末裔は当然、寺子屋のように破壊されたくはないのである。
しかし、皮肉なことに、今や彼らの一部、例えば給特法で残業代のない彼ら、臨時採用のままの彼ら自身が、既存のシステムに疲弊し、変革を潜在的に望んでいる。さらに、いじめ被害者、通信制高校の選択者、中退者といった、既存の公教育システムに適合できなかった人々は、その変革に強い賛同を示すだろう。そして何より、住民サービスよりもふるさと納税の返礼品でゆるキャラの鞄か何かを貰いたい人々は、すでに「国民」という共同体への強いコミットメントを失っており、公教育の「国民形成」という役割が希薄になることに対し、抵抗感が小さいか、むしろ歓迎する可能性さえある。彼らは、意識的か無意識的かにかかわらず、公教育の性格変更に「既に」賛成しているのである。
これらの既にある賛同も、公教育とその置かれている環境の対立の先鋭化を示しているが、ここでは対立の先鋭化の結果として言及するに留めよう。
5. 結論:不可避な選択
結局のところ、公教育の現状維持は外部環境の変化から考えるに、不可能なのであり、その未来は二つの根本的な選択肢のいずれかに集約される。公教育そのものを完全に変更するか、外部環境を完全に変更することで公教育を維持するかのどちらかである。
もちろん公教育の性格を変更することに反対するのであれば、それは環境の方のドラスティックでラディカルな変更を意味する。つまり国家にその原初的な性格、戦争機械としての性格を取り戻させることを目指すことになる。それはそれで良いのかも知れない。しかし公教育の再建を唱える者たちにそのような気概があるとは思えない。
このように現代の公教育は、その起源に根差した「国民形成」という重い足枷を外すのか外さないか、外すとすれば新たな時代に即した役割はあるのかという問いへの解答を迫られている。それは、単なる教育改革に留まらず、社会全体のあり方、そして未来の「共同体」の姿を問い直す壮大なプロジェクトとなるだろう。そのような気概のある者たちが現れる前に現場の人々が力尽きて消滅してしまわないことを祈ろう。いや、消滅するべきであろうか。消滅することでしかもはや善きことはありえないとするならば。