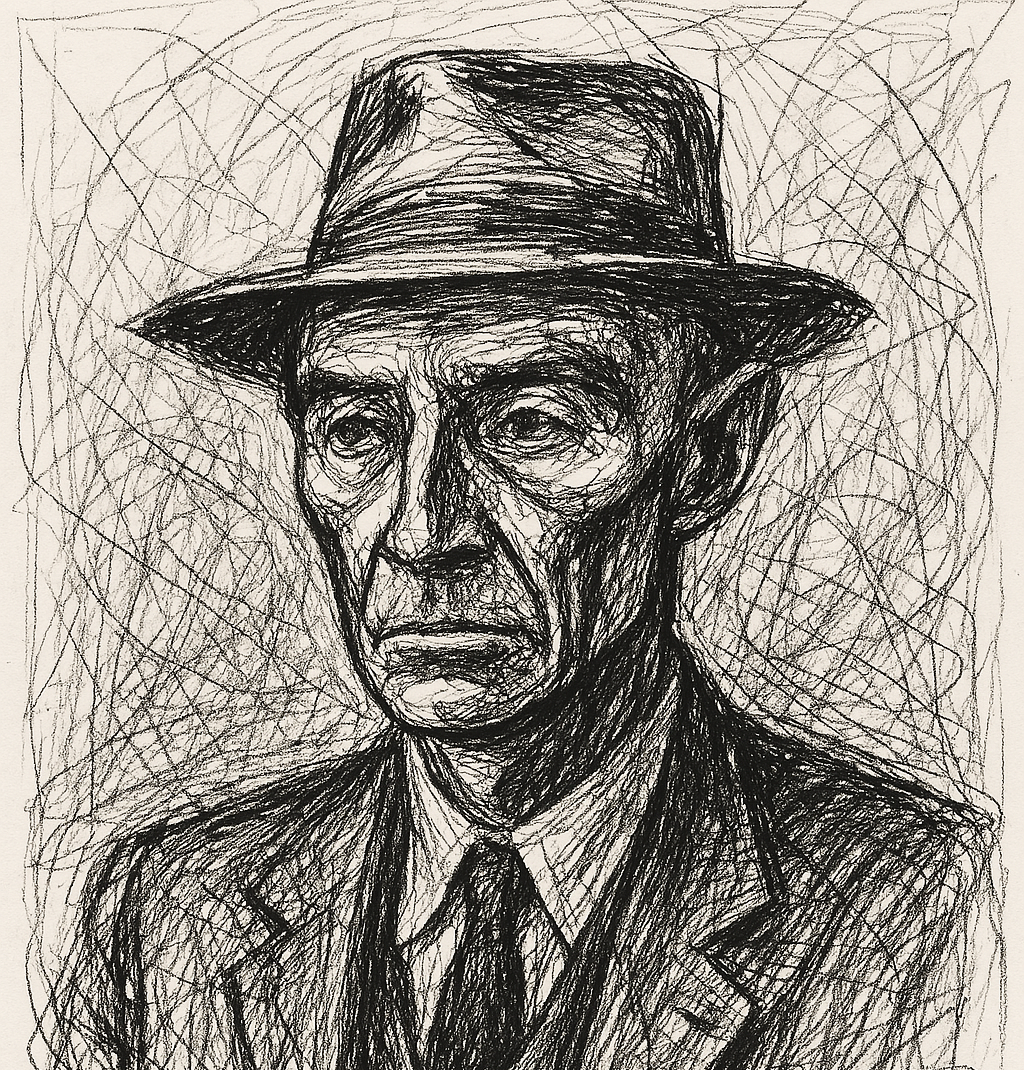Authored by 円原一夫
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、マンハッタン計画を強力に推進したロバート・オッペンハイマーの伝記映画である。『イミテーション・ゲーム』や『ビューティフル・マインド』、『ハンナ・アーレント』のように、学者を主人公にした映画は数多く存在するが、今後、誰かにそのような作品を薦める機会があれば、私は『イミテーション・ゲーム』とこの『オッペンハイマー』を薦めようと思う。伝記映画のカテゴリなら、さらに『マルコムX』を加え、文化人を主人公にした映画も含めるならば『カポーティ』も適しているだろう。
私がこの映画を高く評価する理由は、この作品が「世界が終わった後の世界」を描いているからだ。そう、世界は既に終わっている。驚いたか? いや、あなたは驚いてなどいない。あなたは、世界が既に終わっていることを知っている。世界はもうどうにもならない。悪化することはあっても、良くなることは決してない。知っているだろ? 知らなかったのか? それでは、あなたは人生を丁寧に生きてきたとは言えないだろう。家を出て、五分もすれば、誰だってわかることだ。人類は今、終末後の世界を生きている。この映画は、オッペンハイマーという人間を通じて、その現実を描き出してしまったのだ。「描いてしまった」という表現は、それがノーラン監督の意図とは異なる可能性があることを示唆するために、そうした。しかし、意図など重要ではない。世界は既に終わっているのだから。
劇中、オッペンハイマーは左翼の女性「ジーン」との会話の中でこう語る。
「資本論は読んだ。三巻全部ね。長ったらしかった。こんな言葉があったな──所有は窃盗である」
これに対し、彼女はこう返す。
「財産」
「財産?」
「財産。所有じゃなくて」
オッペンハイマーは続けて言う。
「失礼、ドイツ語の原書で読んだから」
史実のオッペンハイマーも多言語に秀で、複数の言語を使いこなしていた。この場面は、彼がドイツ語で講義を行う場面と同様に、その才能を示している。また、オッペンハイマーが共産主義に関心を持ち、カール・マルクスを原書で読むほどの関心と知識を有していたことを示す場面でもある。しかし同時に、この場面はオッペンハイマー、あるいはノーランの誤りをも示している。しかし、実はここに、この映画の全ての価値を左右する可能性の中心がある。
「所有は窃盗である」というテーゼは、一般的にカール・マルクスではなくピエール=ジョゼフ・プルードンに帰せられるものであり、ここでは明らかにカール・マルクスとプルードンの混同が見られる。
しかし、私はこの場面でジーンのように「財産」と「所有」の違いを指摘したいわけではないし、マルクスとプルードンの差異について語りたいわけではない。また、制作陣の社会主義や無政府主義、左翼思想に対する無知を批判するつもりもない。むしろ、逆である。この否定性が肯定されるとすれば、どのように肯定されうるのかを考えたいのである。それこそが、クリストファー・ノーランの意図を超えた、映画の可能性の中心だからである。
この謎を解き明かすために、もう一つの場面を思い出してみよう。
映画の終盤にオッペンハイマーとアインシュタインの会話が描かれる。かつてオッペンハイマーは、「核爆弾を炸裂させた場合に地球の空気全てが発火する可能性」についてアインシュタインに相談していた。もちろん、世界は滅亡しなかった(地球の空気全てが発火することなしに核実験は成功し、核爆弾が実用化された)。しかし、オッペンハイマーはアインシュタインに「我々は(世界の滅亡を)引き起こした」とアインシュタインに伝える。この言葉には、核兵器の実現によって世界は既に滅亡を先取りしてしまっているという彼の絶望が込められている。彼は無数の弾道ミサイルが発射されるイメージを幻視する。
既に死刑が決まった死刑囚にとって残りの日々はただの消化試合である。これは比喩ではない。死刑囚の残りの日々は死刑を待つためにある。彼は更生可能性がないから死刑囚になったのだ。彼は死刑になるために、健康であること、自殺せずに生きることすら、義務である。核兵器の開発は、ちょうど世界を死刑囚にしたのである。世界は死刑の日をただ、待っているのだ。オッペンハイマーはそれを理解してしまった。世界の滅亡のビジョンを見ない者には、彼は戦前と戦後で主張の一貫性を失い、支離滅裂な言動をしているようにしか思えない。しかし、懲役囚と死刑囚とで、死生観が同じであることを期待するのは誤りである。
マルクスも、プルードンも、その他のオルタナティブも、既に滅んだ世界には何の意味もないのではないかという問い。この映画の可能性の中心とはそれである。人類は一線を超えている。財産と所有、マルクスとプルードン、原本か邦訳か。そんなことに、今や何の意味があるというのか。死刑が確定したのだから。何もかもが無意味になる時は、既に。アポカリプス・ナウ。