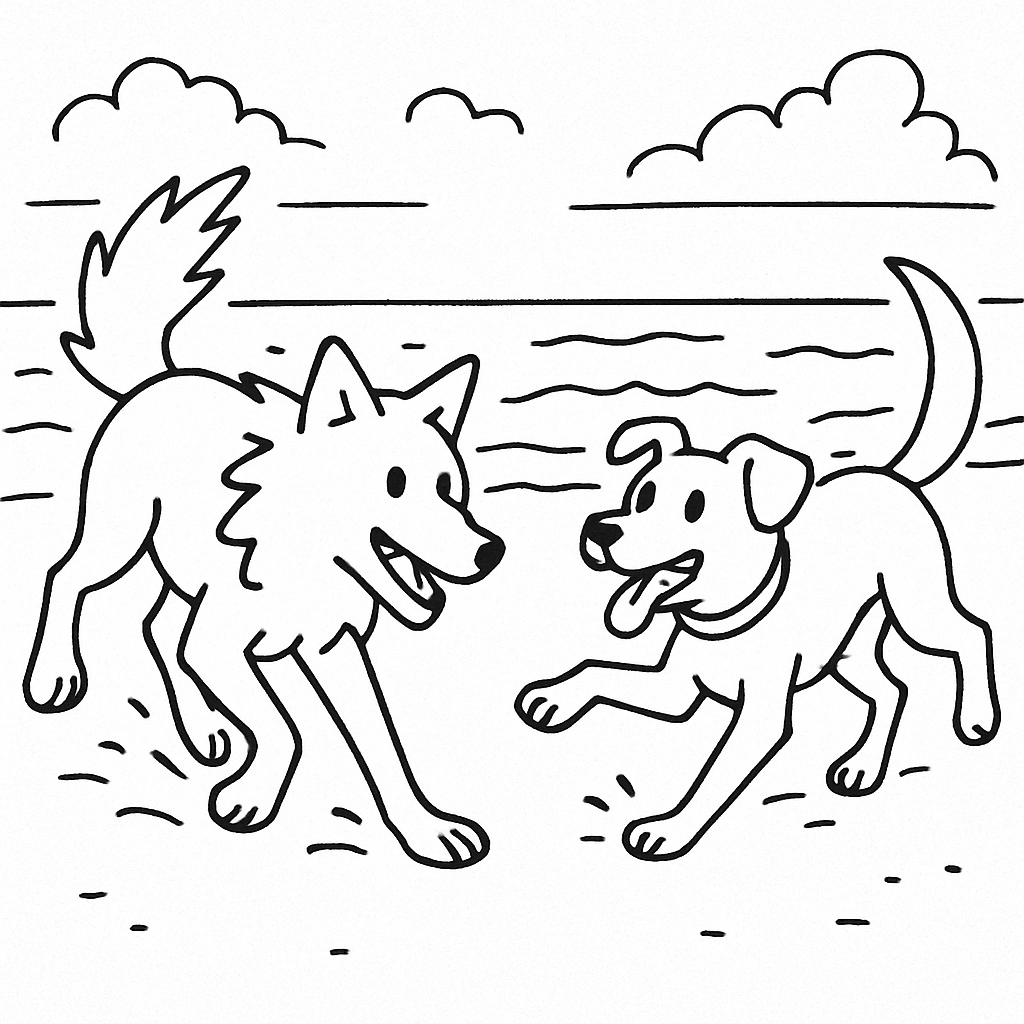Authored by 円原一夫
下記の文章は、私の記憶では十年近く前に書いたものであるが、私がある作品を批評するという時に(現在時点で)最も重視していることを先取りしているため、私がいつでも自分の基準点を思い出すことができるように、あえて、ここに掲載するものである。
私が重視しているのは、対象となる作品をプロパガンダの叩き台にするのではなく、その作品がその内部に持つ、ある決定の不可能性、解決不可能な矛盾を発見し、スポットライトを当てることであり、言い換えれば、ある作品を二重、三重に味わうことができるようにすることである。
この論考で私は、細田守監督作品『おおかみこどもの雨と雪』にメロドラマとメロドラマへの抵抗の両方が同時に見て取れることを明らかにしよう。「同時に」。そうしたメッセージの二重性、複数性が映画の豊穣さ、「映画」をプロパガンダから区別するものだと思うが、そうした議論はここではしない。
映画のタイトルからわかるとおり、この映画は「おおかみこども」の雨と雪を巡る物語であるが、それにしても、「おおかみこども」というものについては絶対に説明が必要であるし、その説明を兼ねて、この映画の粗筋をまず書くことにしよう。
後に雨と雪を産む、その母であり、つまり主人公の一人である「花」は東京の外れにある国立大学に通う大学生である。これは明示されないが、その建築物などから、東京大学であることが黙示されている。これは重要なことだ。彼女は、いわばそこらの普通の男性よりも、相対的に高位な階層にアクセスする権利を有しているということだからである。さて彼女は講義に潜り込んでいた男性の「彼」と出会い、恋に落ちる。ここまでは我々の現実の延長であるが、しかし実は「彼」はニホンオオカミの末裔であり、人間の姿と四足歩行する自然主義的に描かれる狼の姿の二つを自由にとることができる存在であることが明かされる。それでもなお花は「彼」を受け入れ、ついに花は「彼」の子どもを姙娠することになる。その子どもこそ雨と雪であって、この二人もまたその父と同じ特性を有しており、それゆえ父が「狼男」であるのに対し彼らは「おおかみこども」となる。しかし物語が欠如と欠如の回復、混沌と秩序の構築によって構成されているからには、この家庭にも影が忍び寄ってくる。ある日、「彼」がいつまでたっても帰ってこないという事態が起きる。花は「彼」を探しに行くが、「彼」は狼の姿になって河の中で死んでいる。その直接の原因は明確にされない。とにかく「彼」は狼であるから、その「死骸」はゴミ収集車のような物で運び去られてしまう。かくして花と雨と雪は「父」を喪失することになる。物語が駆動し始める。
この「父」を喪失した、ファンタジックな家族がいかに父無き後に秩序を構築するか、ということがこの映画の主題になるわけであるから、まさしくこれはメロドラマということになるだろう。ここで私はあえて、誰か一人にフォーカスするのではなく、この家族の成員全員の、「父」の喪失の処理の仕方を分析していく。それは花と雪と雨ということになるが、まさに三者三様の仕方によってこの事態を乗り越えるのであって、それこそ細田がやりたかったことであるはずであるから、私はそれぞれを比較しつつ、分析しよう。
まず花を視てみよう。花は恐るべき人間である。狼とのハーフである「おおかみこども」よりも、花こそよほど人間らしくない。というのは、花は父子家庭の出身であり、さらにその父が死んでいるために、両親という一種の財産的余力を全く持たないにも関わらず、「彼」を受け入れ、その子どもを姙娠し、何の屈託も葛藤もなく、「母」となる。さらに「彼」が死んだ後にも、この花が「母」という役そのものを放棄したいと願うとか、その重責に悶え、「母」ではない自己を探究し始めるということは全くないのである。花の「父」なき混沌の乗り越えは単純である。それは花がひたすら「母」という役割を、相対化し意識の対象とするような「役割」としてではなく、自然なものとして受け入れ、奮闘するという内容である。これは完全に肯定的なものとして描かれ、ついに全て報われる。花は子どもたちのために(東京大学であることが黙示されている)大学を中退し、過剰に元気な「おおかみこども」が暮らすのは難しい都会から田舎へ引っ越し、都会よりむしろ異質な他者に不寛容でありそうな田舎で彼女は地域住民の信頼を獲得していく。ここにあるのは吐き気を催すほど、「男」にとって好都合な「女」であるが、花には「母」であることの葛藤が存在しないので、視聴者はそういうことを意識しないで済む。だが「おおかみこども」の二人の「父」なき混沌の乗り越えはこれほど単純ではない。特に雪は雄の身体を持つ「おおかみこども」であり、花の新しいロマンスの相手となるキャラクタが不在であるから、彼は「父」となることが宿命づけられている。この映画がメロドラマの文法に忠実であることによって。
この映画は三人の成熟の過程を描くことで一見して複雑そうな物語構造をとっているが、極めてメロドラマの文法に忠実である。その点で面白いのは、狼男の成熟した男性である「彼」がいかに成熟までを、その狼と人間の中間足る身体でありながらやり抜けたのかという知識の継承に失敗しているという点である。そのため劇中には「(狼と人間の中間の存在が)どうやって成長してきたのかちゃんと聞いておけば良かった」といった内容の台詞さえある。まさにここに父の不在による混沌がある。さて雨と雪はいかに父の不在を乗り越え、成熟するのか。こうしてメロドラマが、いかにジェンダー規範を身につけるのか、というドラマが作動することになる。実際、雨と雪が物語中で苦悶するのは、ジェンダー規範の獲得という課題のためである。しかし後に詳述することになるが、雨はジェンダー規範の獲得に失敗し、その失敗と「おおかみこども」という特性が組み合わさることで、一種のアクロバティックな「成熟」を成し遂げることになる。さて、それでは雨と雪はどのようにその課題と戦うのか。
雪は人間の雌の身体を持つ「おおかみこども」であり、非常に活動的な子どもである。彼女は家の周りを狼の姿で駆けまわり、猪や野良猫と喧嘩をする。彼女もやがて小学校に通うことになる。そこで低学年の内こそ運動ができることによって人気者となるが、彼女の狼性は(「男は狼なのよ」という歌もあるように)本能の壊れた動物としての人間の中では男性性と解釈されてしまう。例えば彼女の「宝物」は動物の骨やトカゲの干物であるが、当然、それは同級生の少女たちの間では受け入れられない。そこで彼女は「女の子」らしくあるために、ほとんど恐ろしいほどに「良き母」である花に「青いワンピース」を作ってもらい、同級生たちに「可愛い」と言われ、その輪に再び入ることに成功し、「これに本当に助けられ」る。彼女は狼性を隠匿することで、一度、女性性を獲得する。しかし、それを脅かす存在が現れる。転校生の「草平くん」だ。彼は彼女に「犬でも飼っているのか」「けものくさい」と、特に告発するつもりもなく言うが、それは彼女にとってあの隠匿した狼性、男性性を指摘されることに等しいのであって、彼女は「狼」狽し、ついに彼にその年頃の少女にはありえないほど強い暴力を行使し、草平を沈黙させる。彼女にとって、それは男性性の隠匿の失敗に他ならないために、彼女は人間の中で生活すること、女性性を獲得することに失敗したと思い込み、一時的に不登校になる、だが草平は彼女の隠匿しているものを理解し、受け入れ、彼女と彼女が「おおかみこども」であるという秘密を共有する。彼女はこの「男」と秘密を共有し、帰属するジェンダーを安定させ、物語の終わりには「良き母」足る花のもとを離れて、都会の寮がある中学校に進学する。彼女は社会の中でいかに振る舞うべきかという規範、特にジェンダー規範の内面化に成功したのだ。これは勿論、肯定的に描かれる。中学校の校門の前、笑顔の花と彼女のツーショット、そしてナレーション。映画が終わる。だが、私の文章は終わらず、雨と「課題」の抗争を見ていくことになる。あるいは、雨の戦いこそ、この映画をメロドラマによる支配から救済しているということを。
雨の成長過程はメロドラマの枠内における一種のアクロバットになっている。どういうことか。雨は雪とは違って、人間の雄の身体を持つ「おおかみこども」である。しかし彼は雪とは反対に、大人しい性格であって、雪に「狼らしくない」といったことを言われるような性格である。狼らしくない、というのは、人間社会においては「男らしくない」ことに翻訳されうる特性であって、雪は、雨が後に女性性との間で葛藤を生むことになるほど活発な子どもであるのに対し、授業中は教室の後ろでじっとしていて、授業時間外は廊下で他の子どもに「いじめ」の類と思しき行為を受ける短いシーンが挿入されるような子どもであって、その時には雪に助けられてさえいる。雨は人間社会に溶け込むこと、言い換えれば男性性の獲得に失敗していることが強調され、ついに不登校になる。雪もまた不登校になっているが、彼女は草平との間で「秘密を共有し」、彼に受容されることで、安定した女性性を獲得するのに対し、雨はついに人間社会に溶け込むこと、男性性を獲得することを完全に断念する。この断念は雨が「おおかみこども」であるという設定によって、端的なものとして、つまり雨が小学校ではなく、山の主である狐のもとに通い、狼の何たるかを教わり、ついに人間ではなく、狼として生活するようになる、という形で現れることになる。いわば雨は男性性の獲得に断念し、その代わりに、狼である自己に目覚め、動物というジェンダーの未分化である地点へ移行するのである。これが、この移行こそが、メロドラマへの抗いなのだ。しかしここで注意したいのは、雨は山の主である狐の役割を継承し、山に秩序をもたらす存在つまり、人間社会の「父」に相当するものになったとも解釈可能であるということだ。ただし、その解釈は、我々が動物の世界に我々自身を投影する時にだけ成立可能なものである。
まとめよう。『おおかみこどもの雨と雪』は、直接の父を喪うことで、象徴の「父」をも喪った「おおかみこども」たちとその母の混沌に陥った世界がジェンダー化という劇中で徹底的に祝福される過程を経ることで再びその眼前の世界に秩序をもたらし、特に人間の雄の身体を持つ雨は山の主の地位を継承することで山に秩序をもたらす者すなわち「父」となる。これは完全にメロドラマの文法に従ったものであって、典型的であるということができる。しかし、我々が動物の世界に我々を投影しなければ、雨はジェンダーの未分化な地点に移動したのであると解釈することができるのであり、この映画にメロドラマと同時にメロドラマとの闘争を見て取ることができるようになる。